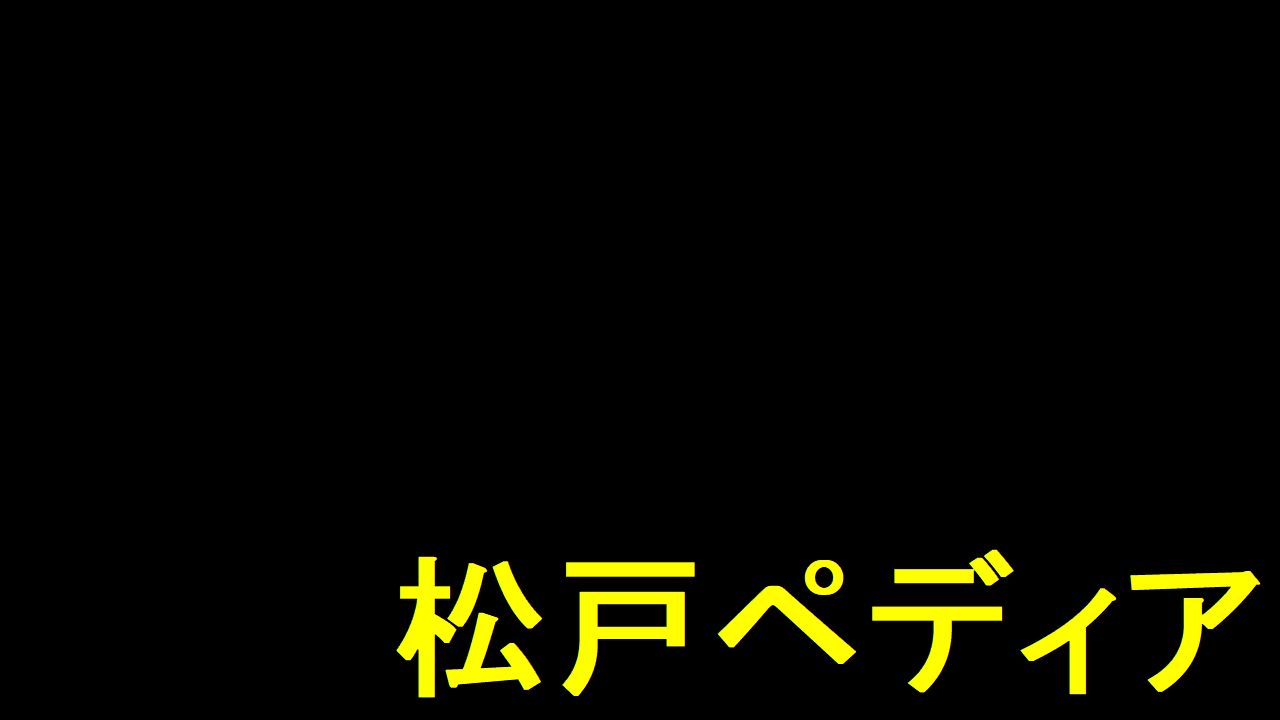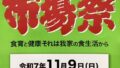私が学生だった40年前にはすでに人工知能のソフトあったんですよ。これ書いてて思い出した。
漢字は忘れたのですが「そうげん」というソフト。
その頃から将棋ソフトもあったのですがバカ弱かった。それが今ではプロ棋士とも互角以上というかそれ以上に強くなってしまった。隔世の感があります。
このレポートはAIに以下のXのポストを投げて、書いてもらったのを加筆訂正しました。
これからは学校の宿題で読書感想文意味ないですよ。
AIが書いたか人間が書いたかわからない。
松戸ペディアのサイトで各学校へのリンク貼ってあるので一度ご覧になってみてはいかがでしょうか(なお松戸ペディアでは記載のない学校についても調べてできる限り表示しています) https://matsudo-traveller.com/matsudonavi/
最近歩いて松戸市内の全小中高と特別支援学校合計81校の校門・校舎の写真撮りました。その中で松戸市立の小中は65校(高校は市松のみ)あります。全ての学校のウェブサイト拝見しています。みなさんは関係のある学校のウェブサイトご覧になったことありますか?65校の内、沿革(創立年月日など学校の歴…
— 松戸ペディア (@matsu_traveller) October 8, 2025
松戸市立の学校のウェブサイトのどこに問題があったかというと設計段階の誤りです。そもそも全体のサイトを作った業者(=テンプレートを作成した業者)に各校が基本データ(沿革、校歌など)を投げて業者に入力させれば良かったのです。そうすればデータの抜けがなくなります。それを各校に任せてそれ…
— 松戸ペディア (@matsu_traveller) October 8, 2025
調査概要と背景
本レポートは、松戸市内の全小・中・高校および特別支援学校(合計81校)の校門・校舎写真撮影および全校ウェブサイトの閲覧調査に基づき、特に松戸市立小中学校(小45校・中20校)の計65校のウェブサイトの情報公開状況を分析した結果をまとめたものです。
(このレポートは2025年10月8日のXへのポスト時点の調べによるものです。)
この調査でわかったことは、学校ごとの情報公開に対する姿勢、すなわち「情熱の差」を浮き彫りにしています。
調査結果:学校ウェブサイトの情報記載状況
松戸市立の小中学校計65校のウェブサイトを詳細に調査した結果、学校の歴史や伝統に関する基本的な情報の記載に、大きな偏りが見られました。
| 項目 | 記載のない学校数(65校中) | 記載率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 沿革(創立年月日など) | 17校 | 約74% | 学校のルーツに関する基本的な情報 |
| 校歌 | 18校 | 約72% | 学校の精神・文化の象徴 |
主要な発見
- 沿革(創立年月日)の欠落: 17校において、学校の創立年月日や簡単な沿革の記載が見られませんでした。これは、「創立記念日を祝うにもかかわらず、創立の根拠となる情報をウェブサイトで公開していない」という矛盾を内包しており、学校の歴史に対する意識の低さを示す可能性があります。
- 校歌の未掲載: 18校で校歌(歌詞または音源)の記載がありませんでした。校歌は、学校の教育目標や理念、地域の風景などを伝える重要な文化遺産であり、その情報公開に対する消極的な姿勢がうかがえます。
現状が示す根本的な課題と考察
本調査結果は、単に個々の学校の努力不足を示すものではなく、ウェブサイトの運用における初期設計と組織的なチェック体制に根本的な問題があったことを示唆しています。
1. ウェブサイト初期設計におけるプロセスの誤り
ウェブサイト作成において、基本データ(沿革、創立年月日、校歌など)の収集・入力作業を各学校の裁量に任せたことが、情報に抜けが生じた最大の原因です。
- 管轄組織の責任: テンプレートを作成した時点でそれを管理・監督する管轄組織が、本来一括で集められるべき基本データを初期段階で全て入力完了させるプロセスとすべきでした。
- チェック体制の不備: 基本情報の抜け漏れについて、学校側も、その上の管轄組織も、公開前の最終チェックを怠った結果、学校間の情報格差が固定化されてしまいました。
2. コンテンツの「情熱格差」と学校の可能性
ウェブサイトの内容充実度は、担当する教職員の熱意に大きく依存しているのが現状です。学校は、年間を通じて様々な行事や学習活動が行われる「ネタの宝庫」であり、担当者が運営を楽しいと感じるほど、その熱量がウェブサイトに反映され、内容が充実していきます。しかし、その「情熱」が個人の負担に依存している現状では、持続性や均一性に欠けます。
3. 歴史・伝統の継承と情報提供の不足
沿革や校歌といった基本的な情報がないことは、卒業生や地域社会との精神的なつながりを弱めるだけでなく、学校の歴史やルーツを知る機会を在校生から奪いかねません。また、地域住民や転入を検討する家庭にとって、学校の教育理念や文化を把握する妨げとなっています。
結論と具体的な提言
今回の調査で明確になった組織的な課題と個人の情熱の格差を解消し、全ての松戸市立学校のウェブサイトを活性化させるための提言を以下に示します。
提言1:基本情報の整備とチェック体制の確立
- 基礎情報の必須化: 松戸市教育委員会として、創立年月日、沿革、校歌といった学校のアイデンティティに関わる基本的な情報を、全ての市立学校ウェブサイトに必須項目として掲載するガイドラインを直ちに実行し、未記載校への情報提供を求めるべきです。
- 一元管理の導入: テンプレートの更新やシステム移行時には、基本データを管轄組織が一括で投入・管理し、学校側の作業負担を軽減するとともに、情報の抜けをゼロにする体制を構築すべきです。
提言2:生徒参画によるコンテンツの質向上と競争促進
ウェブサイト運営を一部、生徒に任せることで、コンテンツの質と量の両面で飛躍的な向上が見込めます。
| 施策 | 目的 | 効果 |
|---|---|---|
| 生徒運営委員会・部活動化 | 生徒による写真撮影、記事執筆、レイアウト提案を正式な活動とする。 | 責任感が生まれ、生徒目線の新鮮で魅力的な記事が充実する。 |
| 教職員の役割明確化 | 先生は「コンテンツの確認・承認(校閲)」と「技術サポート」に専念する。 | 教職員の負担軽減と、生徒の主体的な学びの場を創出する。 |
| ウェブサイト・コンテストの実施 | 年に一度、全65校を対象に「デザイン」「情報の鮮度」「魅力度」などを競うコンテストを実施する。 | 学校間の健全な競争意識が生まれ、ウェブサイトのレベルが全体的に底上げされる。 |
生徒を巻き込むことで、ウェブサイトは単なる情報公開ツールから、生徒の表現・学習の場へと進化し、学校全体の活性化へとつなげていくということを提言させていただきます。